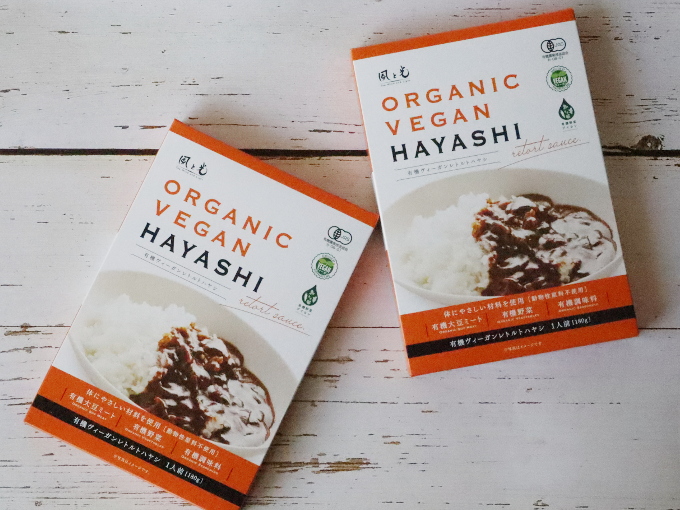北海道産オーガニックビーフを通じて赤身牛肉のおいしさと、棄てるには「もったいない」を牛の餌に変えてフードロス削減にチャレンジする青山商店が、クラウドファンディングサイトCAMP FIREにて発売をスタート!持続可能な循環型社会の実現に貢献する牛肉の生産や、有機畜産の社会的意義を広く知っていただくためのプロジェクトです。
北海道の大地が育む赤身牛肉の魅力を伝えるため、今回は青山商店が販売する2つの農場をご紹介。同じ北海道でもそれぞれの地域の風土にあった飼育をしており、飼育方法も餌も違います。それぞれの肉質や風味の違いを感じていただけるよう、今回のリターンでは食べ比べもご用意しています。
■有機牛肉100%グラスフェッドビーフ(北海道・八雲町)
※グラスフェッド=牧草で飼育
■釧路生まれ、釧路育ちのオーガニックビーフ(北海道・釧路市)
▽クラウドファンディングCAMP FIRE
【オーガニック牛×フードロス削減】地球も牛も人も幸せな社会を作りたい
https://camp-fire.jp/projects/752339/view
希少な国産オーガニックビーフ
オーガニックビーフと名乗ることができるのは、農林水産省が定める「有機畜産物の日本農林規格(JAS有機畜産)」の認証を受けている畜産、加工を経た牛肉だけです。日本ではオーガニック畜産物の生産はごくわずか!有機牛肉については年間で24トンの生産量(令和2年度)に過ぎません。同年度の牛肉生産量がおよそ33万トンですから、国産牛肉のうちオーガニックビーフはわずか0.007%です。
オーガニックでは、環境や人間、社会、そして畜産動物の行動欲求にも配慮することが求められます。群れで暮らし、歩き回り、草を食べ、水を飲み、母が子を育てる。牛として本来当たり前の欲求にしたがって行動できる最も配慮された環境が、放牧主体の畜産であり、こうした配慮することも原則のひとつとしているのが、オーガニックビーフ(有機畜産)なのです。

オーガニック牛×フードロス削減
青山商店と榛澤牧場が手を組み誕生した「釧路生まれ、釧路育ちのオーガニックビーフ」。釧路市の郊外にある榛澤牧場で、約20頭に限り特別な有機アンガス牛を育てています。
釧路生まれ、釧路育ちのオーガニックビーフは、生まれてからおよそ6ヶ月間を親子放牧で育ちます。日本の肉牛生産では子牛が産まれると母親から初乳を与えたのち母親から離し、代用乳を与えて育てるのが主流ですが、オーガニックビーフの子牛は、母牛のお乳を飲み続けて育ちます。
およそ6ヶ月間を親子放牧で過ごした後、牛舎の中で肉牛として肥らせる肥育段階に入ります。肥育期間中も牛舎の中だけで育てるのではなく、牛が屋外に遊びに行けるようにしています。また牛舎の環境もオーガニック基準にのっとり、牛がストレスを感じないゆったりした広さを確保しています。

この肥育の段階で、棄てるには“もったいない”、食品の製造時にどうしても発生する、いわゆる未利用資源を活用した餌が与えられます。オーガニックビーフに与える飼料は当然、原料となるその未利用資源もオーガニックでなければなりません。有機醤油かすや有機おからなどの食品加工残渣、そして、本来なら廃棄される賞味期限切れやエラーでハネられたナッツ類など、すべて有機認証を取得しているものが使われています。つまり、牛たちはオーガニック食品を食べて育っているということ!
もちろん、牛に与える飼料は、牛を健康に保ち、また健全に大きくなってもらうことができるものでなければなりません。飼料のプロである青山商店が、餌のブレンドと設計を綿密に組み立てています。
まず、その土地が育む草を与える。草以外の飼料も、なるべく近くにある、人間が利用できない資源を活用する。それによって、人間の暮らしが農業や畜産を通じて自然と調和し、持続可能な循環型社会の実現に貢献する・・・。
北海道の大地で育ったオーガニックビーフを通じて、こうした価値とおいしさを未来に伝えていきたい。そう願っています。

北海道の雄大な放牧地で、ゆったりと青草を食べながら暮らす牛たちは、おいしい草を探して食べながら歩き回ります。適度な運動は、うま味がたっぷり詰まった鮮やかな赤身の筋肉をもたらします。「釧路生まれ、釧路育ちのオーガニックビーフ」は、やわらかく、リッチで上品な香りがありながら、さっぱりしているのが特徴。その美味しさと肉質が評価され、第12回北海道肉専用種枝肉共励会の最優秀賞も受賞しました。

100%有機牧草で育つグラスフェッドビーフ
グラスフェッドビーフは基本的には牧草(仔牛のときは母乳と牧草)だけを食べて育ちます。その肉質は赤身がとても多く脂肪が黄色いのも特徴です。良質な草を求めて放牧地を運動するので、しっかりめの歯ごたえと自然を凝縮したような肉本来の旨味が魅力です。
草を食べて育った牛の排泄物は、牧草地に還元され、草を育みます。イネ科の牧草が育つための窒素分は、マメ科のクローバー(根粒菌)が大気中から土中に取り込んでくれます。
牧場の外から持ち込むものがないので、牧草は完全に有機飼料。資源循環型の牛肉の国内自給率向上を目指し、八雲牧場から出荷される100%牧草育ちの有機牛肉をぜひご賞味ください。

循環する“しあわせ”な食を未来に
草を食べて育つ牛たち。人間が食べるものと競合せず、むしろ環境コストをかけて廃棄してきた「もったいない資源」を、食べることにより再び人間の食べものにしてくれる牛たち。
未利用資源を活用した牛肉を食べることが、環境や社会、経済、さまざまな課題の解決につながる選択になる可能性があります。
この考え方は、農業や資源のサイクルにも共通して言える、地球規模の大切な視点だと私たちは考えています。
地球も牛も人間も“しあわせ”な未来を目指すために、私たちが取り組む北海道オーガニックビーフをぜひご支援ください!
▽クラウドファンディングCAMP FIRE
【オーガニック牛×フードロス削減】地球も牛も人も幸せな社会を作りたい
https://camp-fire.jp/projects/752339/view